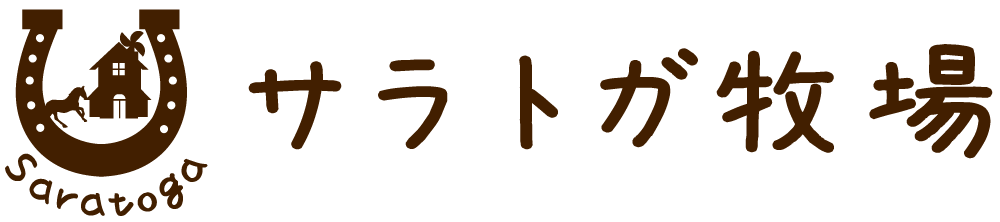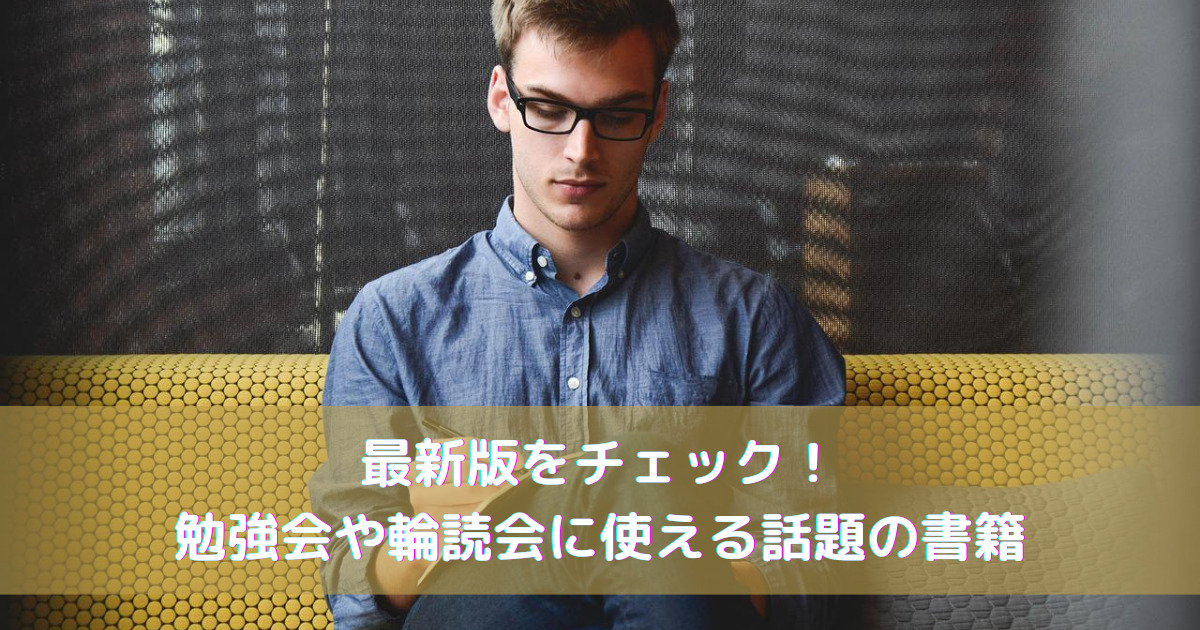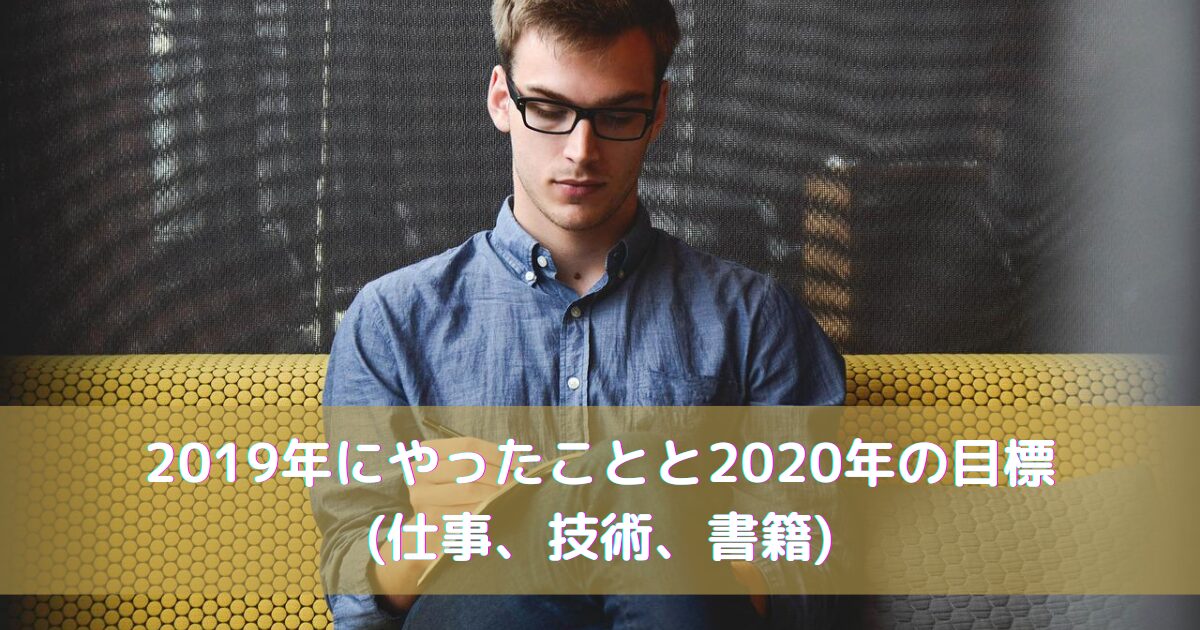最新版をチェック!勉強会や輪読会に使える話題の書籍
毎年恒例の「ITエンジニア本大賞」
振り返ってみると、新しい話題の本から数年に渡って人気の定番本まで、幅広いジャンルの本が揃っています。
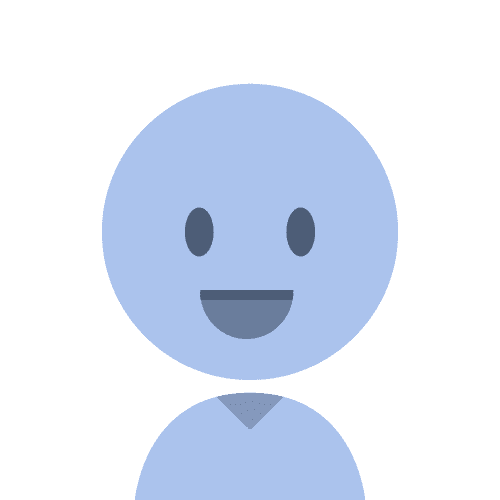
来期の勉強会で使う本、どれがいいかな?
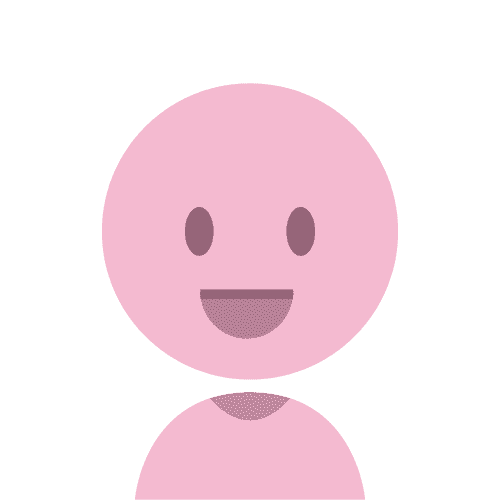
業務に直結するものもいいけど、新しくスキル開拓してみたいな
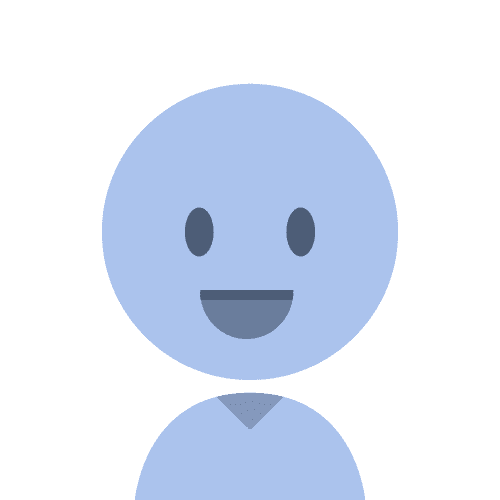
技術だけじゃなくてビジネス寄りの知識も増やしたいな
勉強会を開催する際、最初に悩むのが「テーマ」ですよね。
業務内であれ業務外であれ、何人もの人が勉強会に参加すれば多くの時間が消費されます。
できることなら参加者全員が意欲的に取り組める本をベースにしたいですし、だからといって難易度が低すぎても困りもの。
今回は、エンジニアが選ぶ「技術書」について、最新の情報をキャッチアップしていきます。
ITエンジニア本大賞について
この 1 年を振り返って、
・仕事の役に立った本
・初学者におすすめの本
・ずっと手元に置いておきたい本
などなど、あなたが選ぶ「おすすめの本」というやつですね。
ノミネートされた本の中から、技術書部門とビジネス書部門のそれぞれで大賞が決まります。
過去のノミネート作品については以下で紹介しています。



では、2023 年の年初に発表された技術書のベスト 10 を紹介します。
1冊ですべて身につくJavaScript入門講座
「1冊ですべて身につく JavaScript 入門講座」は、初心者から中級者までを対象とした JavaScript の学習書。
基本的な文法から始まり、オブジェクト指向、非同期処理、DOM 操作、イベントハンドリングなど、実際の開発で必要となる幅広いトピックをカバーしています。
また、各章の終わりには実践的な演習問題が設けられており、読者は理論だけでなく実際のコーディングスキルも身につけることが可能。
この書籍を通じて、読者は JavaScript の基礎知識から実践的なスキルまでを効率的に学ぶことができます。
AWS運用入門
「AWS 運用入門」は、Amazon Web Services(AWS)の運用に必要な知識とスキルを身につけるための一冊です。
本書では、AWS の基本的な概念から始まり、EC2、S3、RDS、VPC などの主要なサービスの設定と運用方法について詳しく解説しています。
また、セキュリティ対策、コスト最適化、トラブルシューティングなど、運用の現場で必要となるテーマも豊富に扱っているのが特徴。
各章の終わりには実践的な演習問題もあり、理論だけでなく実際の運用スキルも身につけることができます。
AWS の運用を始める方や、スキルをブラッシュアップしたい方におすすめの一冊です。
エンジニアのための実践SYMBOLブロックチェーンアプリケーション
「エンジニアのための実践 SYMBOL ブロックチェーンアプリケーション」は、ブロックチェーン技術に興味があるエンジニア向けの実践的なガイドブックです。
本書では、NEM の次世代ブロックチェーンプラットフォームである SYMBOL を使用したアプリケーション開発について詳しく解説しています。
基本的なブロックチェーンの概念から始まり、SYMBOL の特性、ネットワーク、スマートコントラクトの作成方法、トークン作成、トランザクション処理など、具体的な開発手法を学ぶことが可能。
また、実際の開発プロジェクトを通じて、理論だけでなく実践的なスキルも身につけることができます。
ブロックチェーン技術を活用したいエンジニアにおすすめの一冊です。
「技術書」の読書術
「技術書の読書術」は、エンジニアや IT 関連の専門職を目指す人々に向けた読書ガイドです。
技術書は情報量が多く、一般的な読書方法では消化しきれないことが多いです。
本書では、そうした技術書の読み方、理解の深め方、そして記憶に残すためのテクニックを解説しています。
読書計画の立て方からノートの取り方、復習の仕方まで、具体的なステップとともに示されているのが特徴。
また、理解を深めるための質問の立て方や、新しい知識を既存の知識と結びつける方法など、効果的な学習法も紹介されています。
技術書から最大限の価値を引き出したい方におすすめの一冊です。
Good Code, Bad Code
「Good Code, Bad Code」は、ソフトウェア開発者がより良いコードを書くための実用的なガイドブックです。
本書は、プログラミングのベストプラクティスとアンチパターンを詳しく解説し、読者に良いコードと悪いコードの違いを理解させます。
また、コードの可読性、効率性、保守性を向上させるための具体的なテクニックとストラテジーも提供してくれているのがポイント。
さらに、実際のコード例を通じて、これらの原則をどのように適用するかを示しています。
この書籍は、初心者から経験豊富な開発者まで、全てのソフトウェア開発者が自身のコーディングスキルを向上させるのに役立つ一冊です。
スタッフエンジニア マネジメントを超えるリーダーシップ
「スタッフエンジニア マネジメントを超えるリーダーシップ」は、エンジニアリングの世界でリーダーシップを発揮するためのガイドブックです。
本書では、マネジメントポジションではないが、技術的な視点で影響力を持つ「スタッフエンジニア」の役割とその進化について詳しく解説しています。
また、技術的な専門性を深め、組織全体の意思決定に影響を与えるための戦略やスキルも提供しているのが特徴。
さらに、リーダーシップの発揮方法、チームとのコミュニケーション、キャリアパスの設計など、具体的なアドバイスも豊富に含まれています。
この書籍は、リーダーシップを発揮し、自身のキャリアを次のレベルに引き上げたいエンジニアにとって貴重な一冊です。
単体テストの考え方/使い方
「単体テストの考え方/使い方」は、ソフトウェア開発の重要なフェーズである単体テストに関する包括的なガイドブックです。
本書では、単体テストの目的と重要性、設計と実装の最善の方法、そしてテストの自動化について詳しく解説しています。
また、テスト駆動開発(TDD)のアプローチについても触れており、単体テストがソフトウェア開発全体の品質を向上させる方法を示しているのが特徴。
さらに、具体的なコード例を通じて、テストケースの作成方法やテスト結果の解釈方法を学ぶことができます。
この書籍は、単体テストを効果的に活用してソフトウェアの品質を向上させたい開発者にとって、実践的な知識とスキルを提供します。
ちょうぜつソフトウェア設計入門
「ちょうぜつソフトウェア設計入門」は、ソフトウェア設計の基本的な原則と実践的な技術を学ぶための一冊です。
本書では、ソフトウェア設計の全体像を理解するための基本的な概念から、具体的な設計パターン、リファクタリングの方法、テスト駆動開発など、実際の開発現場で役立つスキルまで幅広くカバーしています。
また、読者が理解を深めるための豊富な図解や実際のコード例も提供されているので便利。
この書籍は、ソフトウェア設計の初心者から経験豊富な開発者まで、自身の設計スキルを向上させるのに役立つ一冊です。
評価指標入門
「評価指標入門」は、ビジネスやプロジェクトの成功を測定するための評価指標(KPI)についての基本的なガイドブックです。
本書では、評価指標の選択と設定、その解釈と活用方法について詳しく解説しています。
また、評価指標が組織の目標達成にどのように貢献するか、そしてそれをどのように改善するかについての具体的な戦略とテクニックも提供されているのがポイント。
さらに、実際のビジネスシナリオを通じて、これらの原則をどのように適用するかを示しています。
この書籍は、組織のパフォーマンスを効果的に測定し、改善するための知識とスキルを求めるビジネスプロフェッショナルにとって有益な一冊です。
プログラマー脳
「プログラマー脳 優れたプログラマーになるための認知科学に基づくアプローチ」は、認知科学の視点からプログラミングスキルを向上させるための方法を提供する書籍です。
本書では、プログラマーが日々直面する複雑な問題を解決するための思考プロセスや、記憶、学習、注意力などの認知機能を最大限に活用する方法を解説しています。
また、プログラミングにおけるパターン認識、抽象化、問題解決のスキルを高めるための具体的なテクニックも網羅されているのが特徴。
この書籍は、自身のプログラミングスキルを向上させ、より効率的で生産的なプログラマーになりたいと考える人々にとって、新たな視点とインスピレーションを提供します。
まとめ
勉強会や輪読会など、本をベースにチームメンバーで知見を深める時に役立つものを紹介してきました。
多くのエンジニアが選ぶから良いとは限りませんが、意欲のあるエンジニアの多くが読んでいる本ということで価値があるのは間違いありません。
「これらの本を読めば仕事できる」
そんな甘い世界ではありませんが、エンジニア同士の会話やセミナーなどでの交流など、知識として役に立つ場面は多いでしょう。
チームリーダー的な立場になると、より実感できる部分も多いと思います。
サイバーエージェント(CA)社の「新人エンジニアにおすすめする一冊 2022」の内容もオススメです。